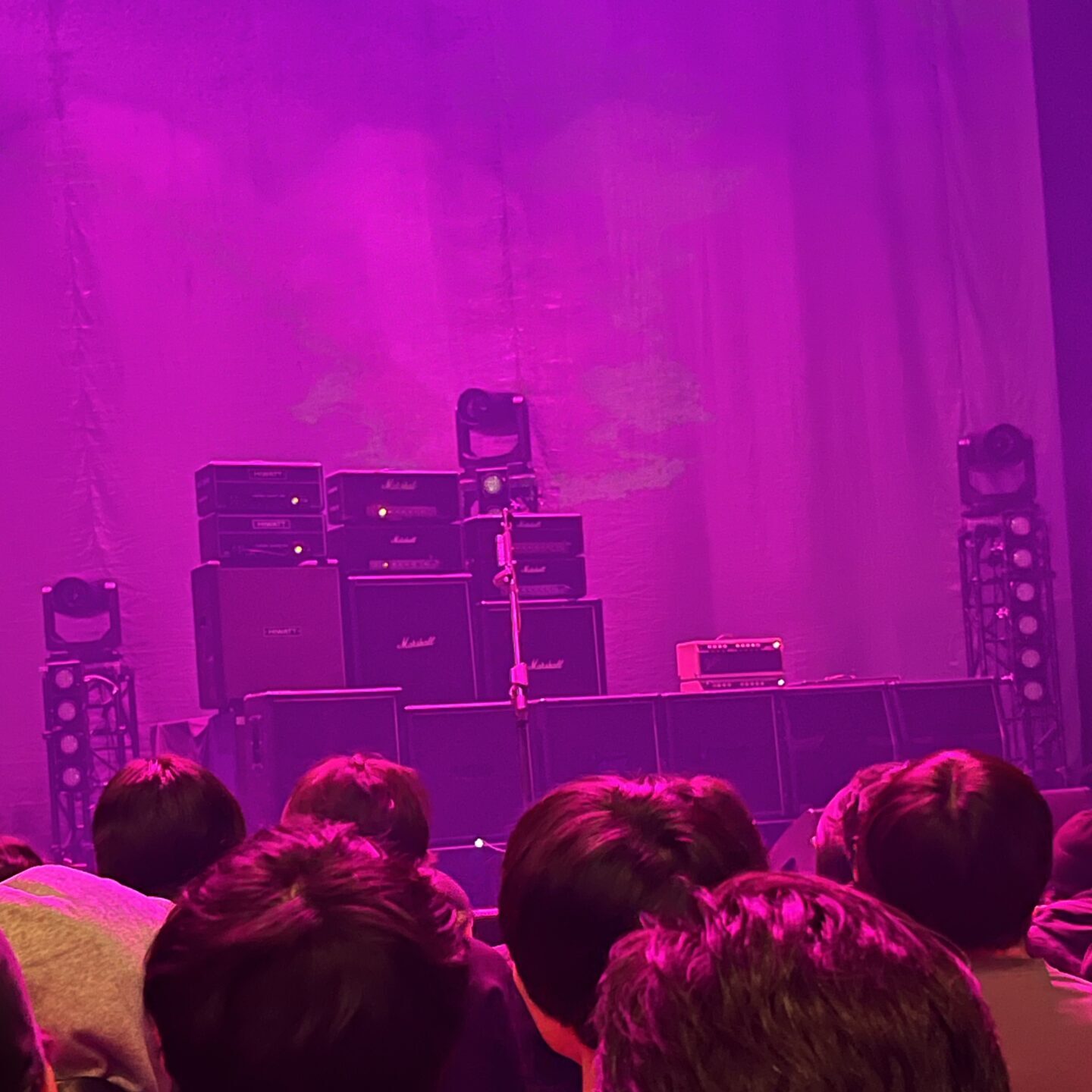7インチ国内盤シングルレコードの『オモシロ邦題の世界』
CONTENTS
どうしてそうなった?!
7インチ国内盤シングル・レコードの
『オモシロ邦題の世界』
時間が無い時でもレコ屋の前を通ってしまうとチェックせずにはいられない、そして最低でも新入荷LPコーナーとシングル・レコードのコーナーは優先的に見てダッシュで次へ進む、レコ屋大好き片山です。
LPももちろん買うのですが、シングル・コレクターでもありまして
今回のコラムはそんな私が個人的に大好きな「シングル・レコード」について書いてみようかなと思ってます。
まずはシングル・レコードの魅力についておさらい
LPと7inchのシングル・レコード(以下シングル)の違いはなんでしょうか?
サイズ?音質? もちろん色々ありますよね。
コレクターさんそれぞれの魅力で感じていただいてるとは思いますが、個人的な感想を。
◆ 大人の収集癖
世代によって様々だとは思いますが子供のころ集めていた ビッグリマンシール、キンケシ、カードダス、ポケモン、週刊誌、単行本、などを集めるような細々な物を集める収集癖が大人になってこのシングルへ移行。
もちろんCDも集めていたのですがネクスト・ステップとしてこちらへ。
たぶん人によっては 楽器、時計、スニーカー、古着、フィギュア、など色々なカルチャーに移行した人もいそうですが、自分はどうやらここへ移行したようです。
◆ 音質
個人的にはそこまで音質にはウルさくないのですが、やはり音圧というかシンプルに音がでかい。
家でLPを聴いていて その後にシングルを聴くと「でかっ」てなりません?
” シングルは構造上LPに比べて溝が広く、場合によっては深めに設計されるため針が音信号を正確に拾いやすくなり音の再現性が向上する傾向がある → ゆえに音が良く聴こえる場合がある ” と言われてますが。
ただシングルによっては逆に音質が悪い商品もあるので注意、というか「シングルは音が良い」とは言い切れません。聴いた個人で決めればいいよね~。好みもあるしね~。と思ってます。
◆ シングルのみでしか聴けない曲
ここがニクイですよね。アーティストやレーベルの意向なのか アルバムとバージョンが違ったり、アルバム未収録だったり、B面曲もアルバム未収録があったり とか。好きなアーティストの度合いが高ければ高いほどシングルも抑えたくなる衝動。シングルのみのモノラル・バージョンが聴きたくなったら完全に沼入り確定ですね。いちいちコレクター心をくすぐるんだよな~。
◆ 場所をとらない。運びやすいのでDJ使いしやすい
買ってもリュックにサラっと入れて帰れるし、たくさん買ってもLPほど帰りの電車も辛くない。LPは重いからたくさん買っちゃうと持って帰るのも大変なんすよ。
そして保管場所もとらない。調子にのってガシガシ買ってたらあらまこんなに?(汗)ってなっちゃう場合もあるけど。
あとDJさんはイベント場所に持っていくのもLPに比べてだいぶ楽ですよね。
◆ デザイン
この時代ならではの文字フォント、色彩、配置デザインはかっこいいですよね。帯は部分的に細長いデザインですが、シングルとなると全方位日本独自デザインですからね。このレトロ感が魅力となります。
◆ サイズ・可愛さ
そしてなんといってもやはり小っちゃくて可愛い。LPのポスター然としたアート的感覚も素晴らしいのですが、やはり小っちゃくて可愛いグッズ感。レコードでありながらカードを集めるコレクト感といいますか。
そして、ある部分に気づくのが…
ここが気になるのよ。そう、これが国内盤シングルのオモシロ・ポイント!
国内盤のレコードには “邦題“という当時メーカーさんが独自につけたキャッチーなタイトル があるのですが、その邦題がLPももちろん面白いのが多いのですがシングルはより如実に現れてる気がして。
たぶん。たぶんですけど。60~70年代当時のアーティストってアルバムが出せなかったシングルのみのアーティストって無茶苦茶存在していて。それを発売するにあたってネットも無い時代だから 有名じゃないアーティストほど情報も少ないだろうし、なんなら曲を聴かずに邦題決めてない?みたいな明らかにズレたシングルもたくさん存在していて。
だけどメーカーはそういった無名の新人&新参者アーティストをどんどん売らにゃいかんし、見て興味をもってもらわないと聴いてもくれんから、
「インパクト勝負!とにかくフックのある邦題を付けねば!」
「勢い大事!誰でもくちずさみたくなるパンチラインを!」
「あのシングルの邦題の波に乗れ!そうすれば売れる!」
といった感じで投げやりとまでは言わないですけど結構強引な邦題が散見される。ここがシングル邦題の面白いとこかな、と思っております。つまりここがオモシロ・ポイント。
60年代はビートルズの勢いが凄まじかったように、それに影響をうけたような同じような邦題もチラチラ。それ以外でも有名バンドの邦題に乗っかったようなシングルもあったりして。
「恋の~」「~のロックンロール」「~天国」「悪魔の~」似たなど似たようなタイトル・シリーズ?を発見。この便乗しまくるスタイルもオモシロ・ポイントと判定。
あと直訳でなくバンド・イメージや曲のサウンドでつけた邦題にも「曲名は置いてけぼり?」なオモシロ・ポイントもあり。
ジャケット・デザインにもオモシロ・ポイントを発見。
邦題に限らず「このアーティスト素材しかなかったの?」と曲調と真逆のデザインにニンマリ。この脱力ジャケ具合にもオモシロ・ポイントとします。
あと無名すぎてアーティスト素材が貰えなかったのか、他のシングルと同じアー写の使いまわしだったり、なんなら素材すらなかったのかイラストでデザインされてたりとか (ソウル系に多い)、そこもオモシロ・ポイントですね。
「なぜ邦題が生まれたのか?」を調べてみたら…
さて、まじめな話、そもそもどうやった経緯で邦題が誕生したのか? 上記までの自分の見解はあっているのか??も気になってきたので調べてみました。
でびっくりしたことに、いざ調べてみるとネットにもあまり情報が無かったのです。 (以下一部引用)
邦題とは、日本以外の 映画名、書籍名、楽曲名 などを日本語で付け直したものである。
~
戦後、日本レコード業界が急速に成長する中で、洋楽の輸入が増加。日本語話者向けにタイトルを「邦訳」する ことで、消費者の理解を促し、売上を伸ばす戦略として定着しました
ウィキペディアですら上記のようにサラッと書いてあるだけで、楽曲名とレコードについて具体的な項目は無し。このページでの説明もレコードの邦題というよりも書籍や映画の邦題?についての印象だったりもします。
(つまりなんらかの関係で映画や書籍からの影響があるということか?) 引用元リンク
ネット上にはオモシロ邦題に触れた記事も数件ありますが、自分とほとんど見解が同じ。かつ経緯についてはほとんど触れていませんでした。意外。
そんな中、当時の状況を伝えてくれる記事を数点発見 (!)しましたので、自分なりの調査結果をお伝えしますね。
邦題決め会議・プレゼンテーションが行われていた!
Guitar Magazineのネット記事「たかが邦題、されど邦題」にて、洋楽ディレクターとして当時の邦題作りに携わっていた田中敏明氏のインタビューが掲載されていました。 (以下一部引用)
~
発売が正式に決定となると編成会議でプレゼンテーションしていました。この段階で洋楽ディレクターはアドヴァンス・シート(当時は手書きでした)にアーティスト名、タイトル、収録曲名、キャッチフレーズ(セールスポイント)を記入していきました。
~
この アドヴァンス・シート(プロモーション資料?)を完成させる段階で、邦題が必要となります。
~
当時ディレクターのデスクには 英和辞典が必需品 として置かれており、日本のマーケットに受け入れられるよう、ヒットを祈願するように洋楽ディレクターは邦題をつける習慣 がありました。
なるほど。あながち考察も大きくズレていないのですが、実際は勢いや直感で独断で作っていたのではなく、社内で会議やプレゼンテーションを行っていたようなのです。
他にも、インタビューでは以下のように語っています。
●邦題をつける際に考慮するものは、原題の意味、アーティストイメージ、歌詞などいろいろあると思いますが、何を重視していましたか?
○ケース・バイ・ケースですね、ジャケットを見てひらめく場合もあれば、歌われている歌詞の意味を考慮する場合もあり、アーティストによりその時々で重視するものは異なります。
●邦題をつける時に心がけていたことは? 売れ行きですか?
○まずは音楽ファンの心に届くこと、売れ行きは結果としてついてくるものに過ぎません。~
●邦題というのは担当ディレクターの裁量で決められるものなのでしょうか? それとも上司や会議などの承認が必要なのですか?
○ ~ まれに上司からもう一考するようにアドヴァンス・シートが突き返されることはありましたし、自分も後輩にそうしたことも一、二度はありました。
●最後に、今でも洋楽に邦題は必要だと思いますか?
○ ~ 洋楽の枠を広げてより大きなヒットにつなげていくには今も必要なケースはあるだろうと思います。
是非インタビューを全文を読んでいただきたいのですが、とても情熱を持って邦題をつけていたことが分かります。自分の見解が恥ずかしさと申し訳なさがこみ上げるほど音楽愛のあるお仕事だったのですね。すみません…。
ただし。ただしですよ。これはあくまでも一例にすぎません。
なのにオモシロ邦題がこれだけ存在するのであれば、メーカーや担当者によっては確信的に付けていた可能性がゼロではないとも解釈できますね。(諦めない俺)
映画の看板やポスターを参考にしていた!
もうひとつは書籍 「洋楽日本盤のレコード・デザイン」 の冒頭コラム 「ビートルズ日本盤ジャケをデザインした男の一人」での竹家鐡平氏のインタビューにて。
竹家鐡平氏はビートルズの「抱きしめたい」「プリーズ・プリーズ・ミー」などの最初期国内盤シングルからの長年シングルのデザインを手掛けておりODEONのロゴも作った凄い方なのですが。
こちらのインタビューではに手書きフォントの書き方や2色刷りからカラーへの移行など作成方法を中心に話が進み、仕事ぶりやどちらかというと当時の状況がわかる面白くも貴重な内容でした。
ただ作る工程のパートでは作成に参考にしたのは映画の看板やポスターだったようで、そうなると先ほどウィキペディアで予想した「映画からの影響」はあるということになりますよね。
たしかに映画の邦題でも「これは…?笑」ていう強引な邦題って昔からあるもんな~。
「 ランボー (原題:First Blood)」や「 ベイマックス (原題:Big Hero 6)」とか「 悪魔の毒々モンスター (原題:The Toxic Avenger)」とか英語タイトルと全然違うしね。
ちなみに下記写真中央の「洋楽日本盤のレコード・デザイン」 以外にも国内盤シングルのアート本やディスクガイド本はいくつか発売されており、中でもこの3冊は邦楽シングルの膨大なバイオグラフィーはもちろん、当時のコレクターさんたちの談話インタビューも節々で掲載されておりオススメです。
さーて、まじめなお話はここまでにして。
それでは本題の「オモシロ邦題の世界」を見てみましょうか。
次ページからは怒涛の紹介ページへと突き進みます♪